なぜ食いしばりが起こるのか?
― 歯・あご・筋肉から見るメカニズム ―
近年、「朝起きるとあごが重い」「歯がしみる」「被せ物がよく外れる」といった症状を訴える方が増えています。
その背景にあるのが、「食いしばり」(ブラキシズムの一種)です。
日中の緊張時や睡眠中など、無意識のうちに強い力で歯を噛みしめてしまうことで、
歯・あご・筋肉に慢性的な負担がかかります。
今回は、食いしばりがどのように起こるのかを、歯科的な視点から解説いたします。
1. 歯にかかる「過剰な力」
歯は本来、食事や会話など“必要なとき”に力を受けるように設計されています。
しかし、食いしばりによって常に強い力が加わると、次のような問題が生じます。
-
歯の摩耗やヒビ割れ
-
詰め物・被せ物の脱離
-
知覚過敏の発症
-
歯周組織への慢性的な負担による炎症促進
こうした状態が続くことで、歯の寿命を縮める原因となることがあります。
2. 顎関節への影響
あごの関節(顎関節)は、上下のあごをスムーズに動かすための繊細な構造をしています。
食いしばりによる長期間の圧力は、関節やその周囲の筋・靭帯に負担を与え、
-
口の開閉時の痛みや音(カクカク音)
-
あごの動きにくさ
-
開口量の減少
といった顎関節症状を引き起こすことがあります。
3. 咬筋・側頭筋などの筋肉への負担
食いしばりの中心となるのは、咬筋(こうきん)や側頭筋(そくとうきん)と呼ばれる咀嚼筋です。
これらの筋肉が長時間緊張状態にあると、
-
顔の張り感(いわゆる「エラが張る」印象)
-
筋肉の疲労やだるさ
-
頭痛、肩こりの誘発
など、口腔外の不快症状を引き起こすことも少なくありません。
このように、食いしばりは全身の筋緊張と関連する症候群としても捉えられています。
4. 食いしばりを引き起こす主な要因
食いしばりの発生には、以下のような複数の要因が関与すると考えられています。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 心理的要因 | ストレス・緊張・集中時の無意識の筋収縮 |
| 咬合要因 | 歯列や被せ物の高さの不調和、咬合干渉 |
| 姿勢・生活習慣 | 長時間のデスクワークやスマートフォン使用による姿勢の崩れ |
| 睡眠時の習癖 | 睡眠中の歯ぎしり・タッピングなどの無意識行動 |
したがって、単一の原因ではなく、複合的な要素が重なって起こるケースが多いのが特徴です。
5. 歯科で行う食いしばりへのアプローチ
歯科では、患者様の症状や原因に応じて、以下のような治療を組み合わせて行います。
-
ナイトガード(スプリント)による歯の保護
-
ボトックス注射による咬筋の過剰な緊張緩和
特にボトックス治療は、過剰に働く咬筋に対して薬剤を微量注入することで、
筋肉の収縮を一時的に抑え、負担を軽減することを目的としています。
その結果、歯の破損や顎関節への負担が減少し、症状の改善が期待できます。
6. まとめ
食いしばりは、「歯」「あご」「筋肉」が複雑に関わり合う機能性の問題です。
放置すると、歯の破折や顎関節症の悪化など、長期的に大きなダメージを引き起こす可能性があります。
症状が疑われる場合は、早期に歯科医師による診査・診断を受け、
適切な治療と生活習慣の見直しを行うことが重要です。
食いしばりや歯ぎしりにお悩みの方・ボトックス治療・ナイトガードに興味のある方
世田谷、桜新町、上用賀・経堂、二子玉川、上町付近で食いしばりや歯ぎしりにお悩みの方は、
世田谷通り りき歯科・矯正歯科にご相談ください。
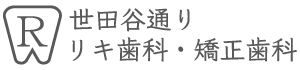

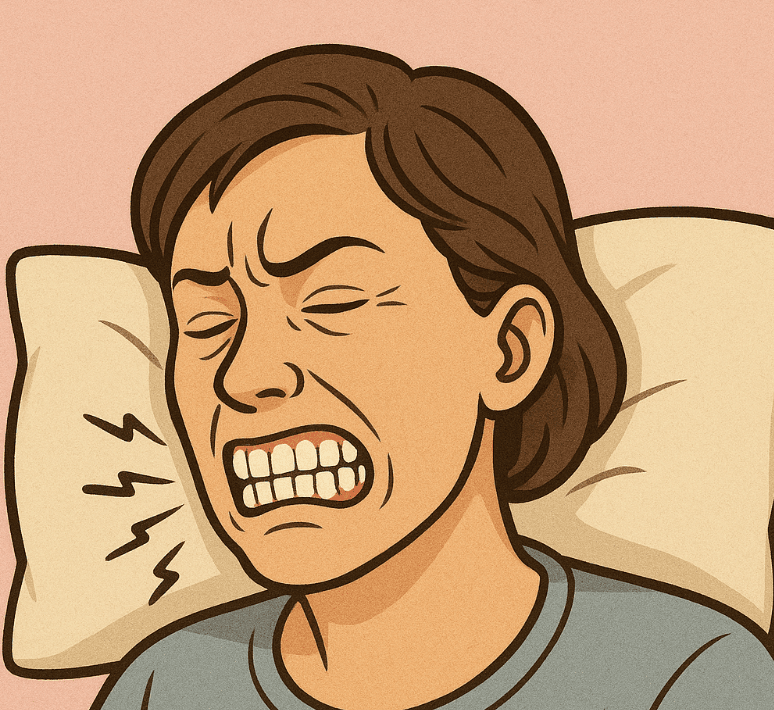








この記事へのコメントはありません。